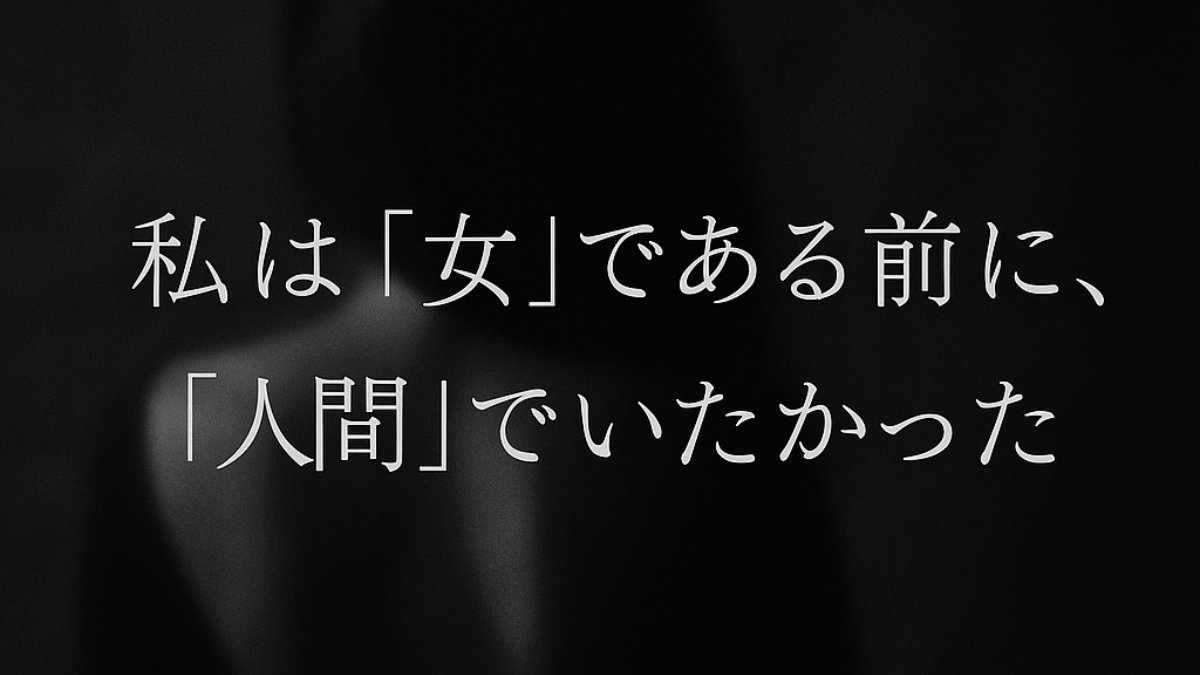事件の「加害者」はひとりでも、責められるのは本人だけとは限らない。家族、恋人、友人——ただ“関係者”というだけで、社会からの非難や偏見の矢が向けられる。
本記事では、加害者家族という立場に置かれた人々の苦しみや葛藤を描いた5つの小説を紹介します。読後に静かに心を揺さぶる、そんな物語たちです。
1. 夜行観覧車(湊かなえ)
登場人物たちは、見栄や周囲の目、自ら描く理想像に縛られ、脆く不安定な場所でかろうじて立ち続けている。彼らは皆、“坂道病”にかかっているかのように、踏ん張らなければすぐに転がってしまいそうなほど危うかった。
実際の生活でも、癇癪を起こす誰かを目にしたとき、見て見ぬふりをしてしまうのが現実かもしれない。本作にはスカッとする展開はない。それでも、それぞれの人物が自らの現実と向き合い、「今何ができるのか」を模索する姿は、確かに胸を打つ。
加害者の家族は、事件に直接関わっていないにもかかわらず、永遠に「加害者」として扱われる。野次馬、ネットでの誹謗中傷、断ち切れないレッテル。とくに、良幸の恋人が彼に向けた態度には疑問が残る。非難する前に、まずは彼の無事を案じるべきではなかったのだろうか。
2. 贖罪(湊かなえ)
物語に一気に引き込まれ、読後にはしばらく感情が整理できなかった。やはり湊かなえの作品は、自分の中の何かを揺さぶってくる。
殺害されたエミリちゃんと、直前まで一緒に遊んでいた4人の少女たち。彼女の母は、「犯人を見つけるか、償うか」と彼女たちに言い残した。その言葉は長く彼女たちの人生に影を落とし、彼女たちは“償い”の名のもとに生き続けることになる。
自分が同じ立場にいたらどうするだろうか。友人が殺され、自分も“あのとき何かできたのでは”という自責の念に苛まれながら、それでも生きていかなければならない。想像を超える恐怖と孤独がそこにはある。
本作では、4人それぞれの心情とその後の人生が丁寧に描かれており、登場人物の一人ひとりに自然と感情移入してしまう。物語としての完成度の高さはもちろん、その根底にある人間のもろさや不条理さが、深く心に残る。
3. 法廷遊戯(五十嵐律人)
現役弁護士である著者が描くこの物語は、他のフィクションと比べても圧倒的なリアリティを感じさせる。法的な描写が丁寧かつ緻密であるがゆえに、内容は決して平易ではなく、読者にも一定の集中力を求めてくる。だが、それこそが本作に没入できる大きな要因でもあった。
美玲にいたずらをしていたのは薫。その行動の背景には、かつての美玲と久我が起こした事件があった。彼らの“犯行”もまた、家庭環境や経済的困窮という逃れがたい事情の中で起きていた。
もし彼らが十分な経済的基盤のある家庭に生まれ、大学へ通うことができ、将来を描く余裕があったなら、あのような道を選ばなかったかもしれない。だが、現実にはそれを止めてくれる大人が周囲にはいなかった。
生まれた瞬間からすでに格差がある——そう思わざるを得ない場面が作中には多くあった。
「法律は誰のためにあるのか?」最近よく耳にする「法律は弱者のためではなく、強者のためにある」という言葉を思い出す。本当にそうなのだろうか。
正当な裁きとは誰によって誰のために行われるのか。冤罪を完全に防ぐことは不可能だとしても、少しでも不幸な判断を減らすために法律が存在するのだと私は信じたい。正義とは、時に残酷で、曖昧だ。
4. 六法推理(五十嵐律人)
本作は「安楽椅子弁護」という構造をとりながらも、登場人物の過去や葛藤に深く切り込んでいく物語である。旧友が関わる火事事件の真相を追い求めながら、主人公は「裁判で勝つこと」と「真実に向き合うこと」のあいだで揺れ動く。
自分がその立場だったら、勝ち目のない裁判を通して、わずかでも“本当のこと”を知ろうとするのだろうか。それとも、確実に手にできる賠償金を選ぶのだろうか。お金があれば、火傷の傷跡は少しでも癒やすことができる。だが、知ることで心が癒やされる保証はない。
正義と現実のあいだに揺れるこの問いは、読む者自身にも突きつけられる。
作中では、他人を信じず、淡々と推理を重ねる姿勢が“真実”に近づいていく手がかりとなっていた。情に流されず、冷静に事実を見極める。その一方で、人は完全に一人では戦えない。何度失敗したとしても、時には誰かに相談し、支えられながら前を向いていくことが大切なのではないか。
法廷という舞台で、どこまで人が人を信じられるのか。裁判が終わった後に何が残るのか。心に静かな余韻を残す作品だった。
まとめ
「加害者の家族」とされた人々は、自らが罪を犯したわけではないにもかかわらず、まるで“共犯者”のような扱いを受ける。彼らが背負わされる重荷は、あまりにも理不尽で、逃れようのないものだ。
今回紹介した小説は、そんな“責められるべきではない人々”に焦点を当てている。
加害者家族という視点を通して、これらの作品は人間の脆さ、社会の構造、正義のあり方について、もう一度考えるきっかけになるかもしれない。
ブログ「読後に残るイヤミスと社会問題」では、他にもさまざまな作品の感想や考察を紹介しています。
SNS更新情報(Xアカウント) → @ひとり読書